宅建登録実務講習の修了試験は、宅建士として登録するための大切なステップです。
合格率は高いと言われますが、「本当に落ちることはないの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、修了試験の基本情報から、落ちる可能性や原因を実際に私も受講した経験をもとにお伝えできたらと思います。
おすすめの講習機関や再試験の情報も紹介しますので、安心して講習に臨めるヒントを見つけてください。
宅建登録実務講習とは?

宅建登録実務講習は、宅地建物取引士試験に合格したものの、実務経験が2年未満の方が資格登録をするために必要な講習です。
この講習を修了することで、実務経験の要件を満たしたとみなされ、宅建士としての登録申請が可能になります。
登録実務講習の目的と内容
登録実務講習の目的は、宅建士として必要な基本的実務能力を身につけることです。
講習内容は、売買契約や賃貸借契約の実務、重要事項説明の作成・説明、契約書類のチェックなど、実務に直結するテーマが中心で、事前学習と集合講習がセットになっています。
対象者と受講資格
登録実務講習の対象者は、宅建試験に合格しているものの、宅建業での実務経験が通算2年に満たない人です。
実務経験が2年以上ある場合は講習は不要ですが、経験が不足している場合は講習修了が登録の条件となるため、事実上必須といえます。
実施機関がまだ決まっていない人はコチラ!
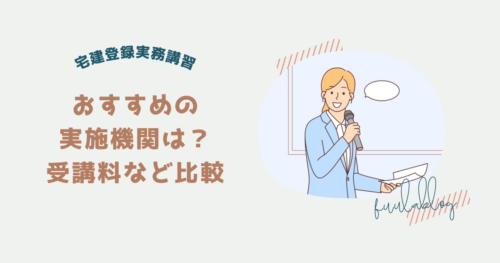
修了試験の基本情報

登録実務講習の修了試験は、講習の最後に行われ、合格しないと修了証がもらえません。
試験は基本的に講習内容から出題され、事前の学習と講習でしっかり理解していれば十分に対応可能です。
ただし、油断すると落ちる可能性もあるため注意が必要です。
試験の形式と出題内容
修了試験は4肢択一式20問と記述式20問で8割以上の得点で修了となります。
出題内容は重要事項説明書の作成・チェック、売買や賃貸の契約実務、法令の基礎知識など、講習中に学んだ内容が中心です。実践的な知識が求められるのが特徴です。
試験時間と合格基準
私が受講した時は試験時間は90分でしたが、実施機関によって異なります。
合格基準は先ほども触れた通り全体の8割程度の正答率が目安とされています。
講習内容をしっかり復習し、重要ポイントを押さえておくことが合格の鍵です。
修了試験は落ちることがある?

修了試験は基本的に講習を受けた人が合格できる内容ですが、油断は禁物です。
合格率は高いものの、落ちる人がいるのも事実で、注意不足や準備不足が原因になることが多いです。
実際の合格率は?
修了試験の合格率はおおむね95~99%といわれています。
とはいえ、誰でも自動的に受かるわけではありません。
講習内容をしっかり理解していない場合や、試験中に焦ってしまうと不合格になるケースもあります。
過去の失敗例や落ちる原因
失敗例として多いのは、講習中の内容を復習せずに試験に臨んだケースや、問題文の読み間違い、時間配分のミスです。
また、解答ミスや見直し不足も要注意。緊張しすぎず、落ち着いて試験に挑むことが大切です。
合格ラインを超えるための注意点
講習中は配布資料や講師の説明にしっかり耳を傾け、重要事項をメモしておきましょう。
それと、テキストに付箋を付けておくと便利ですよ。
試験の時はテキスト持ち込みがOKでしたので、付箋が付いていることですぐに大切な場所がわかるので時間の節約にもなります。
当日は時間配分を意識し、問題を落ち着いて確認しながら進めるのがポイントです。
 フーラー
フーラー実際、私も修了試験に落ちたかも⁉と思うくらい難しく感じました。
おすすめはリーガルマインド!


その理由は…。
宅建登録実務講習の受講先を選ぶ際、おすすめの一つが「リーガルマインド」です。
その理由は、修了試験に万が一落ちた場合でも、再チャレンジができる点にあります。
実は、他の講習機関では一発勝負のケースもあるのでその点は再チャレンジできると思うと気持ちに余裕ができますね。
私自身も別の機関で受講しましたが、修了試験は思ったより難しく、時間配分や問題の読み違えで焦る場面がありました。
これから受講を考えている方は、「万が一」に備えて再試験制度のある機関を選ぶと安心です。
まとめ
宅建登録実務講習の修了試験は高い合格率を誇りますが、油断は禁物です。
試験内容や形式をしっかり把握し、事前にテキストを見直しておくことが合格への近道です。
また、時間配分や問題文の読み間違いといったよくあるミスにも注意が必要です。
さらに、講習機関選びでは、万が一の際に再試験が可能なリーガルマインドのような安心できるところを選ぶのがおすすめです。
正しい準備と心構えで、修了試験に自信を持って挑みましょう。
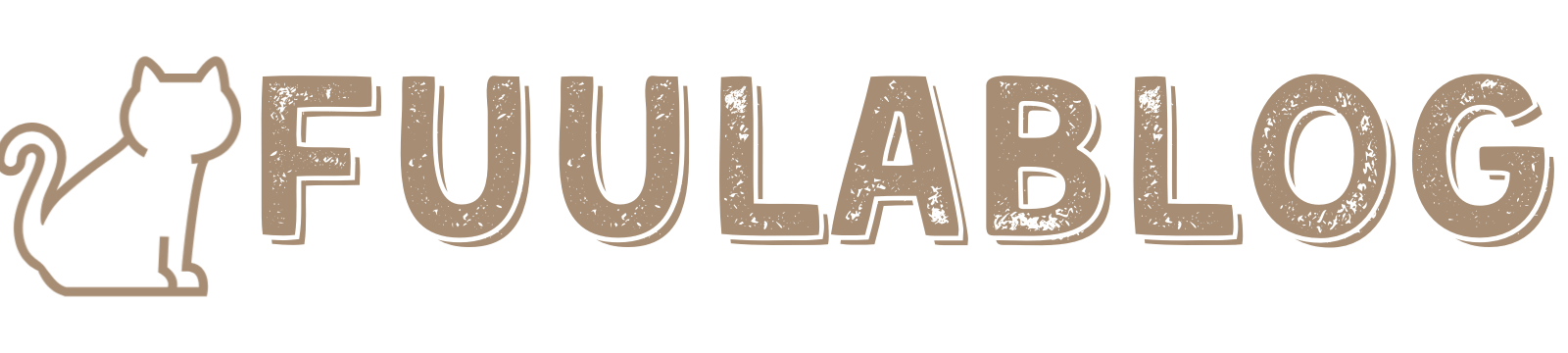











コメント