宅建試験、問1から14までは権利関係(民法)です。
宅建のいちばん難しい分野なので解くのに時間がかかります。
なので問1から解こうとすると、ん?ん?となるかもしれません。それと同時に緊張です。
どんな資格試験でも当日は緊張してしまいますよね。
当日、緊張せずリラックスして試験に臨みたいものです。
宅建試験は工夫が必要です。
問題を解く順番を変えるだけのひと工夫でも全然違うんです。
問1から解かない

問1から解こうとすると権利関係(民法)なので難しいのは当たり前。いきなり難しい問題からスタートしてもモチベーションが下がります。
なので宅建業法から解くのがオススメです。
もしくは、5問免除のところですね。
私は5問免除を受講したので宅建業法から始めました。
その後、法令上の制限に行きましたが思ったより難しく感じてしまい焦りました。わからないなと思った問題はいったん飛ばして大丈夫です。
ですがチェックしておくのを忘れずに。
無解答はもったいないのでまた後で必ず戻って解きましょう。
でも考えてもどうしてもわからない場合もあります。
イチかバチか…そんな時は思い切りも大切かと思います。
宅建5問免除のこと詳しく知りたい方はコチラもぜひ
関連記事>>宅建5問免除はずるい?メリットとデメリット
マークシートの記入は?

1問1問だったり、途中だったり、まとめて最後に塗りつぶすなど人それぞれだと思いますのでどれが正しいかわかりませんがご自身のあったやり方でいいと思います。
ただ、解答と解答用紙がずれたりしないよう気をつけましょう。
試験問題の構成

出題形式
「四肢択一式」問題
50問
マークシート方式
13時~15時までの2時間
13時10分~15時まで1時間50分(5問免除者)
科目ごとの出題数
| 科目 | 出題数 | 問題番号 |
| 権利関係 | 14 | 問1~問14 |
| 法令上の制限 | 8 | 問15~問22 |
| 税・その他 | 3 | 問23~問25 |
| 宅建業法 | 20 | 問26~問45 |
| 免除科目 | 5 | 問46~問50 |
始めに問題をざっと見てから宅建業法の問26から取りかかるのが良さそうです。
出題数も20問といちばん多いので得点源になり易いかと思います。
それと、ひっかけ問題にも注意して下さい。
科目別目標点

| 科目 | 出題数 | 目標点 |
| 権利関係 | 14 | 7~8問 |
| 法令上の制限 | 8 | 5~6問 |
| 税・その他 | 3 | 2問 |
| 宅建業法 | 20 | 17~18問 |
| 免除科目 | 5 | 4~5問 |
目標点数に近づくようにがんばりましょう。
宅建試験は35点前後で推移しますので35点以上は絶対に確保しておきたいところですね。
時間配分は?

50問を2時間で解かないといけないので、おおよそ1問にかける時間は2分以内でしょうね。
最後の見直しにも時間が必要になります。
2分以内という短い時間で答えを導かないといけないので普段からの学習で身に付けるようにしましょう。
最後に
宅建試験の解く順番でのひと工夫をお伝えしました。
普通に問1から解いても構わないのですが、やはり時間の取られる権利関係から始めると調子を狂わされてしまう恐れがあるので、まずはテンポよく解ける宅建業法や自分の得意の分野から始めるのがいいと思います。
時間切れにならないよう、普段から問題を解くスピードには気をつけて下さい。
深呼吸も忘れずに、リラックスして試験に臨めるといいですね。
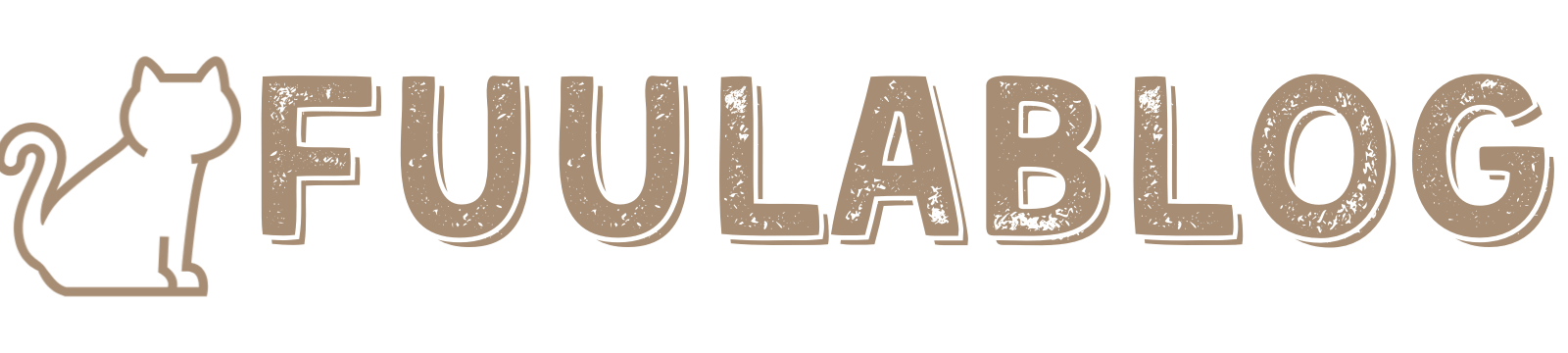



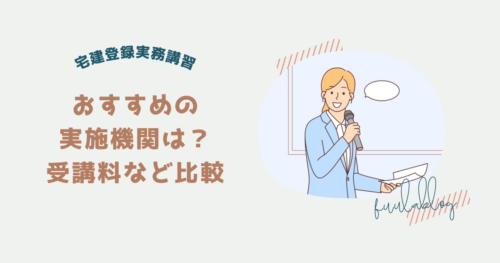
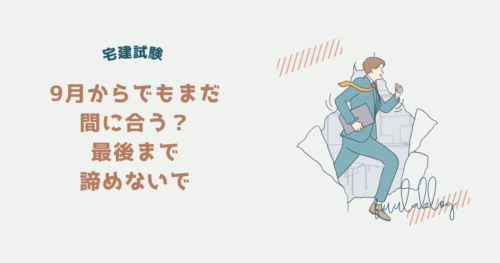
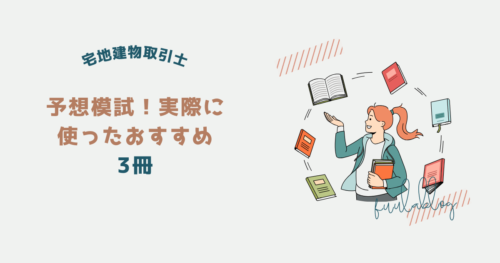
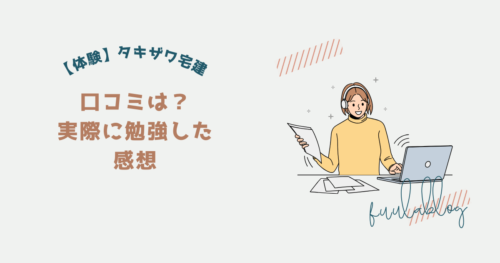
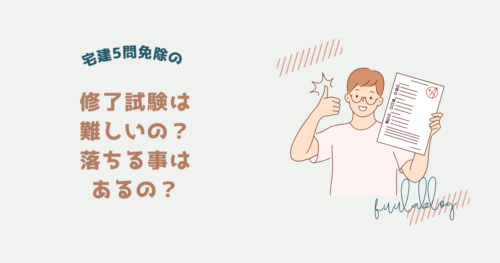
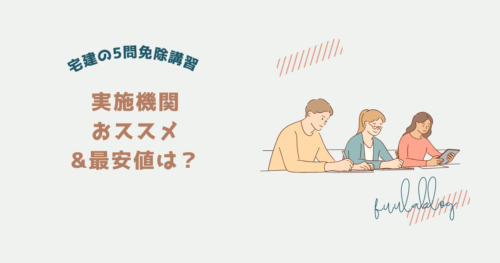
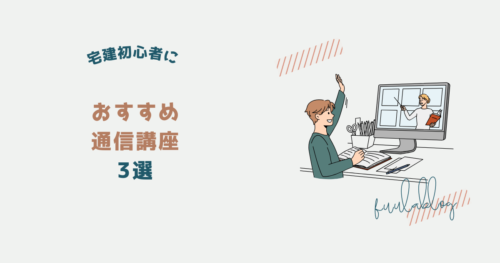
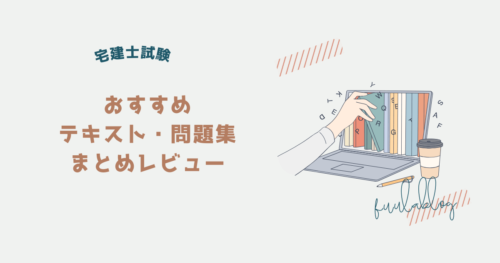
コメント