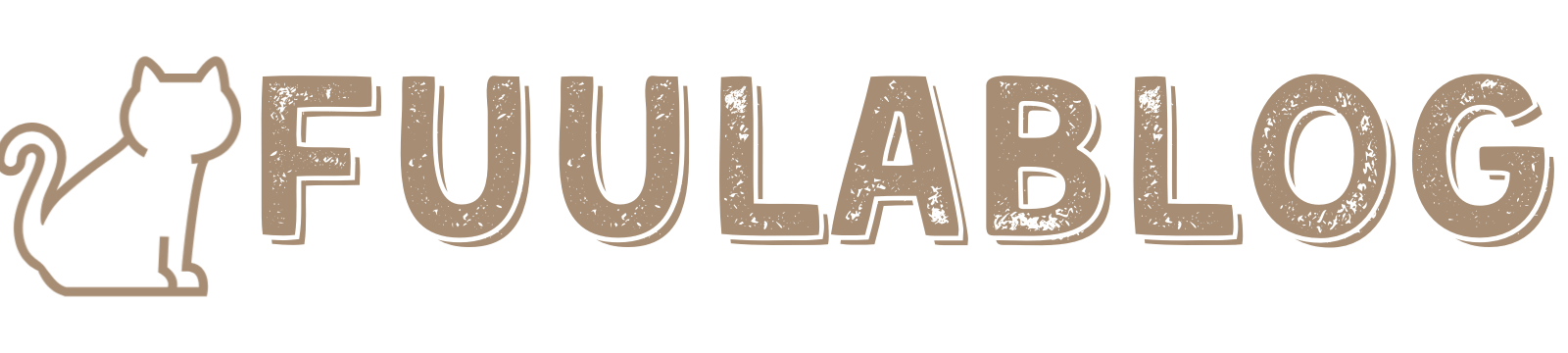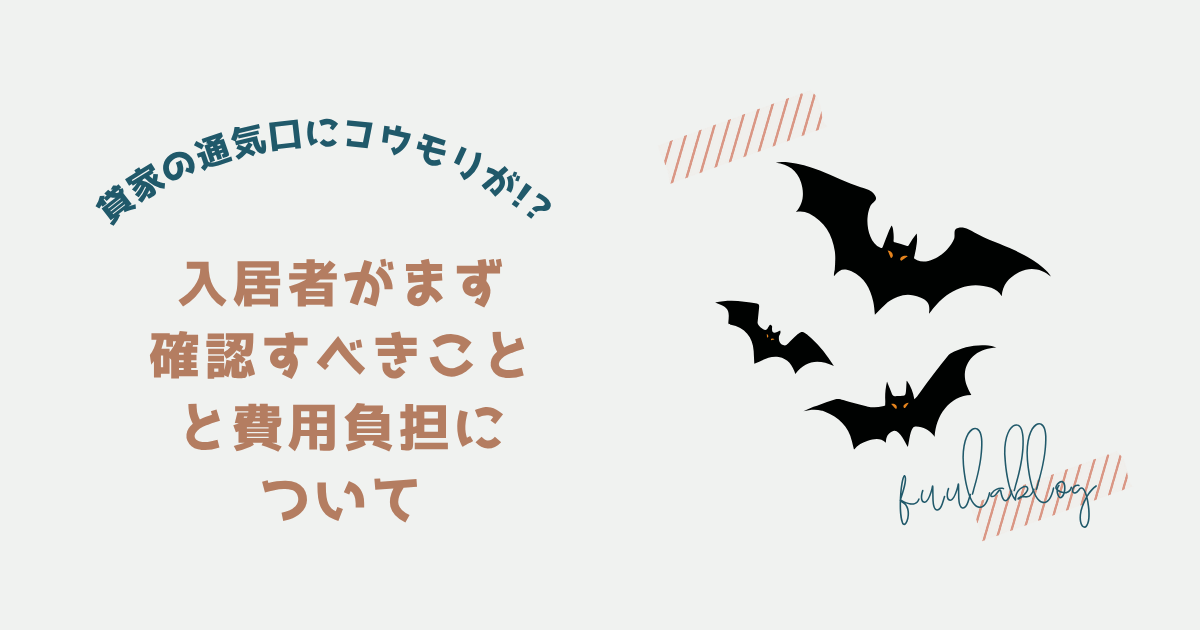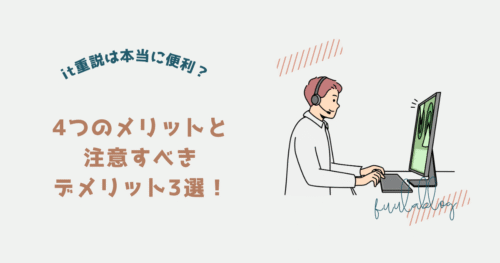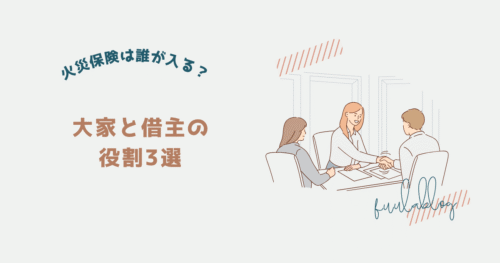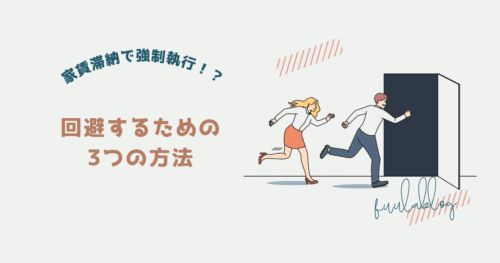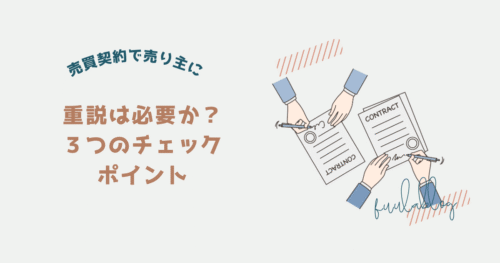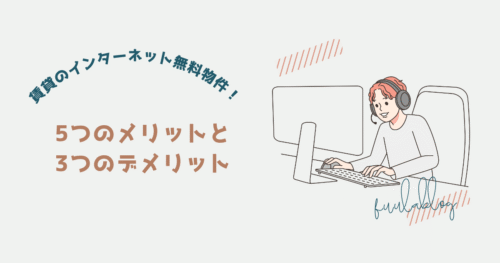「通気口の近くに黒いフンが落ちている」「夜になると屋根裏から音がする」そんな状況に心当たりはありませんか?
それは、貸家にコウモリが住み着いているサインかもしれません。
コウモリは小さな隙間から屋内に侵入し、フンや尿で悪臭や健康被害を引き起こすことがあります。
放置すると被害はどんどん広がるため、早めの対応が重要です。
この記事では、入居者がまず確認すべきポイントや、気になる駆除費用の負担についてわかりやすく解説します。
貸家にコウモリが住み着く原因とは
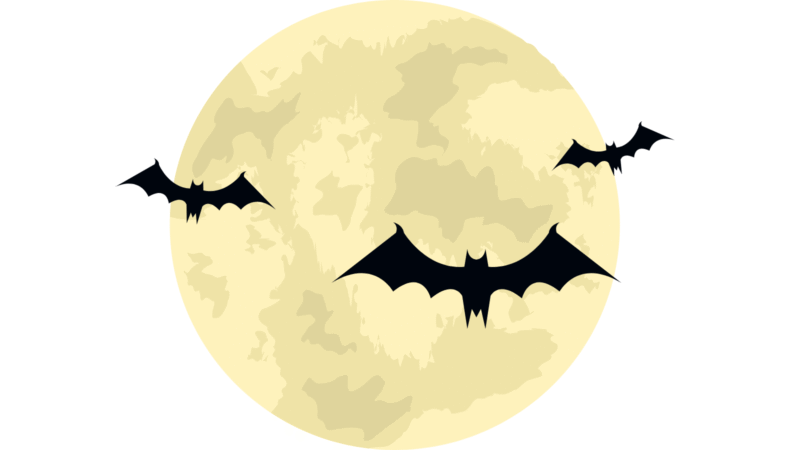
コウモリが好む場所と侵入経路
コウモリは暗くて狭い場所を好むため、通気口や屋根裏、換気扇の隙間などから侵入しやすいです。
外壁や屋根のわずかな穴でも入り込み、巣を作ってしまいます。夜行性で目立ちにくいので発見が遅れがちです。
通気口・屋根裏に入りやすい理由
通気口や屋根裏は外とつながる開口部が多く、わずか2cmほどの隙間があればコウモリは簡単に入れます。
また、外敵から身を守れるため、子育ての場としても選ばれやすい場所です。
平屋の貸家で多い被害事例
平屋の貸家は屋根が低いため、コウモリが通気口や軒下に入りやすいです。
特に築年数が経過した物件は隙間が多く、フンの蓄積や悪臭被害が発生しやすい傾向があります。
コウモリ被害で発生するリスク

フンによる悪臭と健康被害
コウモリのフンは独特の強い臭いを放ち、室内にまで悪臭が広がることがあります。
さらに、フンや尿にはカビや病原菌が含まれ、アレルギーや肺炎など健康被害を引き起こす危険性があります。
室内への侵入で起こる二次被害
通気口や屋根裏に住み着いたコウモリは、やがて室内に迷い込むことがあります。
突然の飛来は入居者を驚かせるだけでなく、家具や壁紙を汚すなど二次被害につながります。
放置することで起こる建物劣化
コウモリが長期間住み着くと、フン尿で木材や断熱材が腐食し、建物全体の劣化が進みます。
通気口の目詰まりや屋根裏の湿気がカビ発生を招く原因にもなります。
コウモリを見つけたら入居者がやるべきこと

まず管理会社へ連絡する理由
コウモリ被害が疑われる場合は、速やかに管理会社へ連絡しましょう。
建物の所有者と連携し、専門業者の手配や費用負担の確認が必要になるからです。
自分で駆除してはいけない理由
コウモリは鳥獣保護法で守られており、許可なく捕獲や駆除を行うと法律違反となります。
さらに、感染症リスクもあるため素人の対応は危険です。
緊急時に入居者ができる応急処置
屋内にコウモリが入った場合は、窓やドアを開けて自然に外へ出すよう誘導しましょう。
素手で触れず、静かに管理会社へ連絡することが大切です。
コウモリ駆除の流れと対応方法

管理会社・業者の調査内容とは
管理会社や専門業者は、まず現地調査を行い被害状況を確認します。
コウモリの侵入口や巣の位置、フンの量などを詳しくチェックして適切な対応策を検討します。
駆除・追い出し作業の具体例
駆除は鳥獣保護法を守り、コウモリを傷つけずに追い出す方法を取ります。
忌避剤や超音波機器を使い、コウモリが自然に屋外へ出るよう誘導する作業が行われます。
侵入口封鎖と再侵入防止策
コウモリの追い出し後は、通気口や屋根裏の隙間をメッシュなどで封鎖します。
侵入口を徹底的に防ぐことで、再び住み着くのを防止できます。定期点検も有効です。
コウモリ駆除の費用と負担について
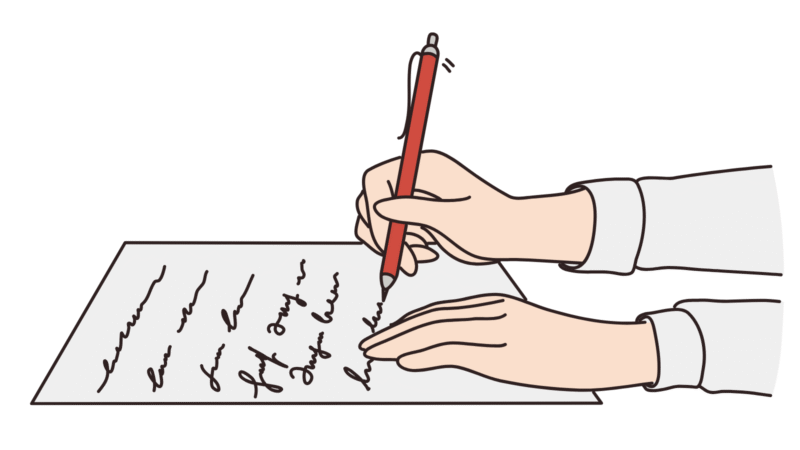
駆除にかかる費用相場
コウモリ駆除の費用は被害状況によりますが、一般的に3万円から10万円程度が目安です。
巣の撤去や侵入口封鎖を含むとさらに費用が高くなる場合もあります。
貸主と入居者の費用負担の違い
建物の老朽化や隙間が原因の場合は貸主負担になることが多いです。
一方、入居者の過失による被害は入居者負担になる可能性があります。
契約書で確認すべきポイント
費用負担の判断は契約内容に左右されます。
「害獣駆除は入居者負担」と記載がある場合は注意が必要です。
トラブル防止のため契約書を確認しましょう。
コウモリ被害を防ぐための予防策

通気口や屋根の定期点検
通気口や屋根は経年劣化で小さな隙間ができやすく、コウモリの侵入口になります。
定期的に点検し、破損やゆるみがあれば早めに修繕することが大切です。
自分でできる簡単な予防法
市販の防鳥ネットや金網で通気口を覆うことで、コウモリの侵入を防げます。
ただし施工ミスは逆効果になるため、慎重に行う必要があります。
プロによる防除施工のメリット
専門業者はコウモリの習性に合わせた最適な防除施工を行います。
侵入口の徹底封鎖や専用資材の使用で、再侵入のリスクを大幅に減らせます。
まとめ
貸家の通気口や屋根裏にコウモリが住み着くと、フンや尿による悪臭や健康被害、建物の劣化などさまざまな問題が発生します。
自分で駆除するのは危険で法律違反になる場合もあるため、まずは管理会社へ相談することが大切です。
費用負担は建物の不具合が原因なら貸主負担になることが多いですが、契約内容の確認も欠かせません。
定期点検や専門業者による防除で再発防止を心がけ、安心できる住環境を守りましょう。