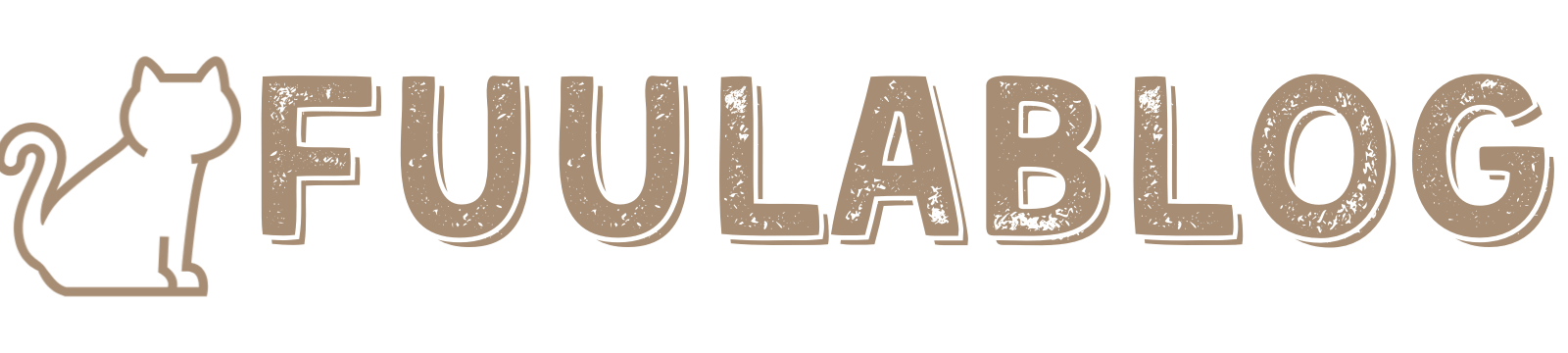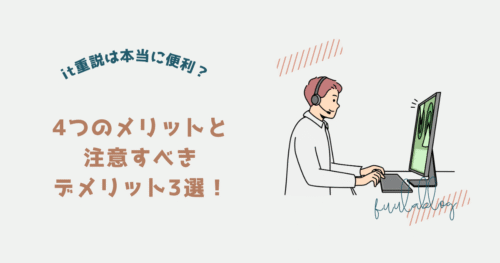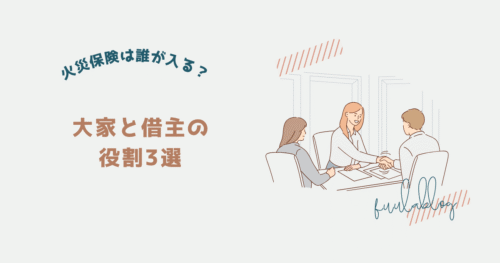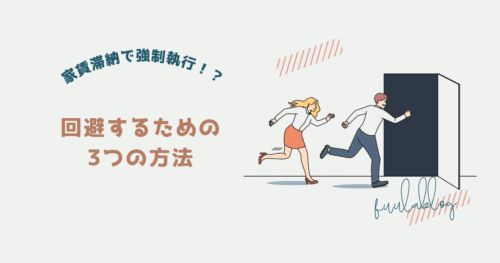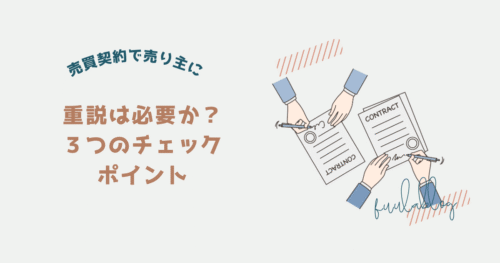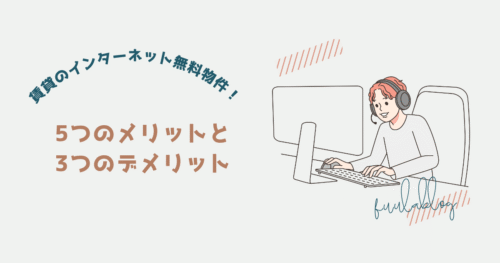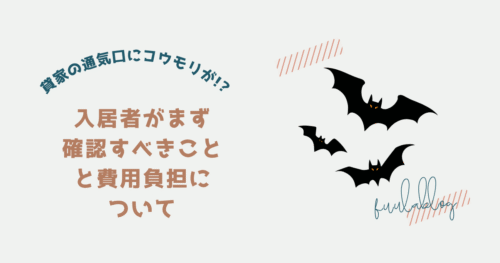賃貸物件で入居者が亡くなった場合、次の入居者にその事実を告知する必要があるのか悩む方も多いでしょう。
特に高齢化が進む中、老衰や病死といった「自然死」のケースが増えており、不動産オーナーや宅建業者にとって告知の有無は重要な問題です。
国土交通省が公表した「人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死の取り扱いや告知義務の範囲が明確化されています。
本記事では、自然死の場合の告知義務の有無や期限、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
自然死でも告知義務があるのか?
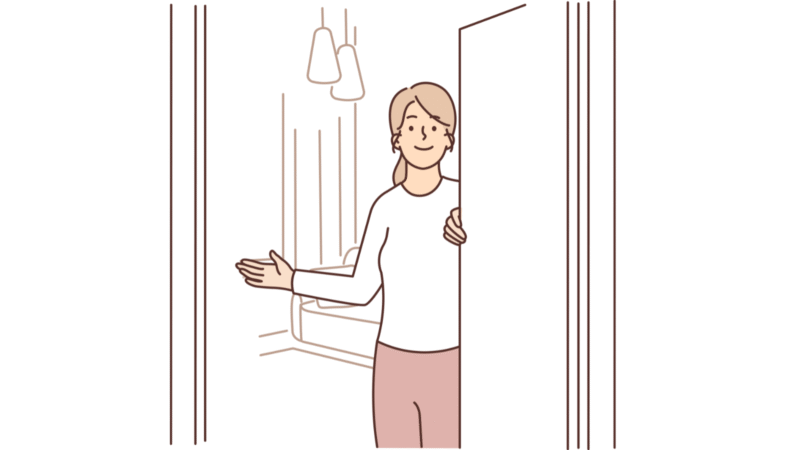
賃貸物件で入居者が亡くなった場合、次の入居者に「告知する義務」があるのかは大きな関心事です。
特に自然死や孤独死では告知の必要性が分かりにくく、トラブルの原因になることもあります。
まずは事故物件との違いや基本ルールを確認しましょう。
事故物件と自然死の違い
「事故物件」とは、自殺・他殺・火災など心理的瑕疵が生じる物件を指します。
一方、老衰や病死などの自然死は原則として事故物件に該当しません。
ただし、孤独死で発見が遅れ腐敗や特殊清掃が必要になった場合は注意が必要です。
なぜ「告知義務」が問題になるのか
不動産取引における「告知義務」は、次の入居者が契約を判断するための重要な情報を提供するために設けられています。
しかし、自然死のように日常的な出来事まで告知が必要なのかは曖昧で、貸主と借主の間で認識がずれることがあります。
賃貸契約における心理的瑕疵の考え方
心理的瑕疵とは、過去にあった出来事が原因で借主が不安を感じるような事情です。
宅建業法では重要事項説明の対象になりますが、自然死は原則として心理的瑕疵に該当しません。
ただし、状況次第では説明が求められるケースもあります。
国交省ガイドラインの概要
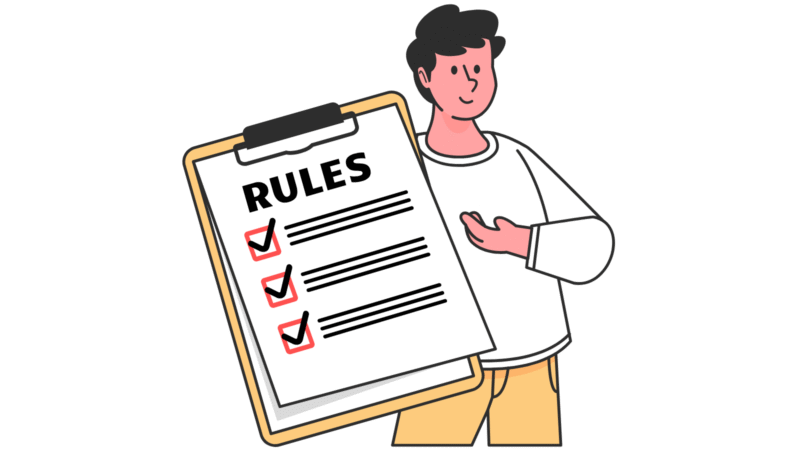
2021年に国土交通省が公表した「人の死の告知に関するガイドライン」は、賃貸・売買における死亡事故の告知義務について明確化したものです。
とくに自然死や孤独死の取り扱いが整理され、不動産取引の実務に影響を与えています。
人の死の告知に関するガイドラインとは
このガイドラインは、宅建業者が賃貸・売買契約の際に「人の死」についてどの範囲まで説明すべきかを示した指針です。
特に曖昧だった自然死・孤独死・事故死の告知の要否を具体的に区分しています。
ガイドラインが定める告知義務の基本ルール
自然死や日常生活中の不慮の死(転倒や誤嚥など)は、原則として告知義務はありません。
一方、他殺・自殺・火災等は心理的瑕疵に該当し、次の入居者への告知が必要とされます。
孤独死は特殊清掃の有無で判断が分かれます。
自然死の定義
ガイドラインでは、老衰や持病による死亡など「日常生活の延長線上で起きる死」を自然死としています。
この場合、特殊清掃を伴わない限り心理的瑕疵に該当せず、原則として宅建業者やオーナーは告知しなくてよいとされています。
賃貸物件での自然死|告知義務は原則なし

国交省のガイドラインでは、賃貸物件で入居者が自然死した場合、次の入居希望者への告知は原則不要とされています。
老衰や病死などは「日常生活の一部」と考えられ、心理的瑕疵に該当しないためです。
自然死・日常生活の不慮の死=告知不要
老衰・病気による死亡のほか、転倒・誤嚥など日常生活上の不慮の死も告知不要とされています。
これは借主にとって特別な不安を引き起こす事情ではないと判断されるためです。
孤独死の場合は?(特殊清掃の有無による違い)
孤独死でも、発見が早く遺体の腐敗や異臭がない場合は自然死と同様に告知不要です。
しかし、発見が遅れ腐敗や汚損で特殊清掃が必要な場合は、心理的瑕疵とみなされ告知義務が発生します。
ガイドライン上の具体例
例として「高齢者が病死し、遺体がすぐに発見されたケース」は告知不要。
一方「発見が遅れ臭気が充満し、特殊清掃を行ったケース」は告知が必要です。
これらは賃貸の重要事項説明書で対応が求められます。
特殊清掃が発生した自然死は告知義務あり

自然死であっても、発見が遅れて遺体が腐敗し、室内に臭いや汚れが残った場合は「特殊清掃」が必要になります。
この場合、心理的瑕疵に該当するとされ、次の入居者への告知義務が発生します。
特殊清掃の定義(腐敗・異臭・汚損等)
特殊清掃とは、遺体の腐敗による体液の処理や異臭の除去、汚損した内装の修繕など通常の清掃を超える作業を指します。
このようなケースは借主に強い心理的抵抗を与えるため告知義務の対象となります。
告知義務の期間:発覚からおおむね3年間
国交省ガイドラインでは、特殊清掃を伴う場合、死亡発覚から「概ね3年間」は告知義務があるとされています。
この期間を過ぎれば告知義務は不要ですが、地域性や事件性によっては例外もあります。
3年経過後の扱いと例外的なケース
原則3年で告知義務はなくなりますが、社会的注目を集めたケースやインターネット上で情報が広まった場合などは、3年を超えても心理的瑕疵が残ると判断されることがあります。
こうした場合は慎重な対応が求められます。
借主から質問があった場合は必ず回答
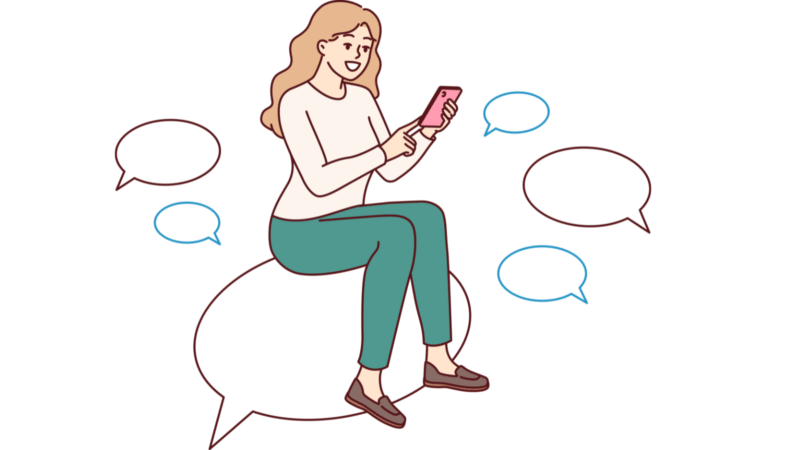
ガイドラインでは、告知義務の有無に関わらず、借主から死亡の有無について質問があった場合は正確に回答するよう求めています。
虚偽や故意の不告知はトラブルや損害賠償請求につながる恐れがあります。
質問義務(告知義務とは別の義務)
告知義務は「特定の事情を自主的に伝える義務」ですが、質問義務は「相手から問われた場合に誠実に答える義務」です。
自然死で告知不要のケースでも、質問があれば事実を隠さず伝える必要があります。
質問時に答えるべき内容と答えなくても良い範囲
回答すべき内容は「死亡の有無」「死因」「特殊清掃の有無」など基本情報です。
ただし、個人情報や遺族に関わるセンシティブな情報まで答える義務はありません。
プライバシー保護も意識しましょう。
「知らなかった」で済むのか?(宅建業者の調査義務の範囲)
宅建業者は売主・貸主に死亡の有無を確認する義務がありますが、それ以上の調査(近隣への聞き込みやネット検索等)は求められていません。
しかし、知り得た情報を故意に伏せることは許されません。
賃貸オーナー・宅建業者が注意すべきポイント

自然死の告知義務は限定的ですが、説明を怠ったことでトラブルに発展するケースもあります。
ガイドラインを理解し、適切な対応を心がけることがオーナー・宅建業者に求められます。
賃貸募集の際の重要事項説明
宅建業法では、心理的瑕疵がある場合は重要事項説明で伝える義務があります。
自然死は原則不要ですが、特殊清掃を伴う場合や過去の死亡事実が広く知られている場合は説明が必要になることもあります。
心理的瑕疵をめぐるトラブル事例
説明不足から「重要事項の不告知」として損害賠償を請求される例もあります。
特にインターネットや近隣住民の口コミで過去の死亡が発覚した場合、借主との信頼関係が崩れるリスクが高まります。
告知義務違反のリスク(損害賠償請求・契約解除)
告知義務を怠ると、契約解除・賃料減額請求・損害賠償といったリスクが発生します。
借主が心理的瑕疵を理由に契約を解除する事例もあるため、誠実な説明が重要です。
まとめ
賃貸物件で入居者が自然死した場合、国土交通省のガイドラインでは原則として告知義務はないとされています。
老衰や病死、転倒や誤嚥といった日常生活の延長線上で起こる死は心理的瑕疵に該当しないため、宅建業者やオーナーは次の入居者に伝える必要はありません。
しかし、発見が遅れ腐敗や異臭が発生し特殊清掃が行われた場合は心理的瑕疵に該当し、死亡発覚から概ね3年間は告知義務が生じます。
また、告知義務がないケースでも借主から質問を受けた場合は正確に回答する義務があるため、情報の取り扱いには注意が必要です。
誤った判断は契約解除や損害賠償につながることもあるため、ガイドラインを正しく理解し、ケースごとに慎重な対応を心がけることが重要です。